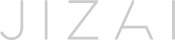木曽漆器の産地に根ざして70年
丸嘉小坂漆器店の挑戦
――素敵な工房にお邪魔しています。
小坂康人(二代目)氏:
丸嘉小坂漆器店は、木曽漆器の産地であるここ木曽平沢(長野県塩尻市)で、家族と4人の職人さんで営む小さな工房です。ここは昔から、中山道の宿場町である贄川宿と奈良井宿の間に位置し間の宿(あいのしゅく)と呼ばれるところで、ふたつの宿場町の需要を満たした漆塗りの産地として栄えてきました。もともと、木曽漆器の上塗師であった初代・嘉男が本家から分家し、1945年に創業したのが始まりです。「丸嘉」の名前は、その初代が由来です。
工房のあるこの建物は、継ぐはずではなかった息子玲央が、同じ仕事をすることになって、建て直したものです。当時、業界は衰退の一途を辿っていましたから、私は正直、自分の代で終わりだと思っていました。ところが、息子の意思に影響され、もう一度挑戦してみようという気持ちが涌き起こり、業務拡大を念頭に建てたもので、私たちの挑戦への決意でもあります。
小坂玲央(三代目)氏:
ここで新旧互いに意見を出し合いながら、ガラスに漆を塗った「すいとうよ」や、色鮮やかな「百色」(ひゃくしき)などの新しい作品や、「woodpia」という健康家具ブランドが生まれていきました。今ではイタリア・ミラノで開催されたコレクションにコラボレーションの形で参加したり、全国各地の百貨店での展示会、東京ビッグサイトでの催し物などにも顔を出したりと、そうやって小さな町から外に出かけては日々動き回っています。
「9ヶ月間仕事なし」
逆境から生まれた新しい取り組み
小坂康人氏:
私がこの世界に入ったのは、家業を継ぐという当たり前の成り行き、流れからでした。家のすぐ隣が工房で、小さいころからずっと初代の仕事を見て育ちました。高校生のころは漆器の需要も高く、学校が休みの日には、私も仕事を手伝っていましたね。継ぐのが当然で、むしろ「迷い」は仕事を始めてから生じました。
初代が58歳のとき、脳血栓で倒れ、いよいよ私が二代目として工房を引き継がなければならなくなりました。いつかはそういう日がやってくるだろうと思っていましたが、それまでしっかりやってくれていた父に、どこか安心していたのかもしれません。突然のことに驚きましたが、とにかくしっかりしなければと腹をくくって、二代目として受け継ぎました。
ところが、引き継いで数年もしないうちに、漆器を取り巻く環境が変化し、9カ月もの間、まったく仕事が入ってこなくなりました。何もしないわけにはいかないので日曜以外は作業をしていたのですが、夫婦ふたり、たまの休みの日曜日に気晴らしにと出かけても、外食のラーメン一杯が食べられないくらい苦しい時期でした。
「辞めよう」「辞められない」の瀬戸際を行き来していたところ、漆器の外商をやっていた義理の父が、新しい仕事を持ってきてくれました。それまで、沈金、蒔絵、呂色塗りなどを専門にやっていましたが、新しい塗りの仕事は、業務用の要素が強いもので、まったくの未経験でした。しかし、それ以外に仕事もないので、とにかく必死になって新しい技法を習得することに。旅館やホテルなど、依頼された仕事はすべて断らずに受け、そうやって徐々に生きを吹き返してきました。事業をやっている以上、浮き沈みは当然ありますが、さすがに9カ月仕事なしというのはこたえました。30歳手前のころです。
猛反対を押し切って漆器の世界へ
親子二代のものづくりの始まり
小坂玲央氏:
そうした「両親ともに忙しく働く姿」を見て、私は育ちました。小さいころは、しょっちゅう仕事場に出入りして木のコマを使って研いだり、塗ったりと仕事の真似ごとをしていたようです。
――玲央さんも、必然的にこの世界に入ろうと?
小坂玲央氏:
私はもともと、医療福祉に興味があり、その分野の大学を卒業し、病院の医療事務の仕事に携わっていました。
小坂康人氏:
私の時は選択肢がなく、せめて息子には自由になって欲しいという気持ちがあったので、「自分の好きなことをやれ」と言っていました。
――自由に進んだ結果、「継ぐ」ことを選ばれたのは。
小坂玲央氏:
身近な当たり前だった父の仕事を、自分が一度外で仕事をすることで、客観的に見られるようになりました。周りから父の評価を聞く機会が増え、当時開いていた個展に足を運ぶうちに、だんだんと木曽漆器に対する価値観や見え方が自分の中で変化していきました。単純に「かっこいい」と憧れを覚えたのです。そして「漆芸作家になりたい」と思うに至りました。
小坂康人氏:
私は、業界が担い手も年々少なくなり将来性は厳しいという状況を知っていたので、当初は反対していました。それに、職人であった私からすれば、息子は想像もできないような初任給、お給料を頂いていたものですから、そんな素晴らしいところをふいにしてまで戻ってくることはないと考えていたのです。
ところが、猛反対する私に同じく塗り師であった妻が、「やりたいものをやらせないで後悔させるか、やらせて後悔させるか、あなたはどっちを選ぶの」と詰め寄られ、「自由にしろ」と言い続けていた手前もあり、この道に進むことを納得しました。