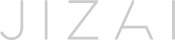紀ノ川に育まれて
――雄大な紀ノ川がすぐそばに流れています。
川崎幹生氏:
私が小さいころは、このあたりの山や川をどろんこになって遊び回っていました。年代もバラバラでガキ大将がいてと、典型的な田舎の風景そのものでしたね。また、外へ出て道を歩けば竿屋さんに会うのが当たり前の光景で……そのくらい、ここでは竿師は普通の職業でした。家には父のお弟子さんも出入りしていまして、そこで働く父の姿を身近に見て、私も「大きくなったら竿師になりたい」と憧れていたものです。
ただ自分は器用ではないと思っていたので、夢はいったんしまい込み、高校生までは普通に過ごしていました。特段目標も無く、そのまま大学へ進み経営学を学んでいましたが、将来は普通の会社員になるんだろうと思っていました。
父から継ぐようにとか、そういった話はありませんでした。この職業を継いでもらおうとは思っていなかったようです。やはり、やりがいだけで語れない厳しさを知っていたからだったと思います。また世の中は大量生産、大量消費に入っていた時代で、職人さんには厳しい時代でした。
ところが、私が二十歳になるころ、一緒に遊んでいた地元の先輩や仲間たちが、二代目として竿師の道へ進むようになり、私も徐々に将来の進路を考えるようになりました。大学へは二時間弱ぐらいかけて通学していたのですが、ある日、地下鉄の階段から地上に上がっていく群衆に揉まれながら、「自分には、こういう生活が出来るだろうか」と問いかけるようになりました。そして、「(厳しくとも)やはり小さいころに憧れていた仕事を目指さないとあかん」と思うようになりました。そこで大学3回生の時に、初めて父に仕事をさせてもらうべくお願いすることにしました。
――ずっと胸の内にしまっていた想いを……。

川崎幹生氏:
緊張しつつも、仕事場へ訪ねて話を切り出しました。「器用じゃないけど……」と口ごもっていた私に対して、父は「器用にこしたことはないけど、大事なのは努力や。不器用でも努力で出来ることがある。そういう自分の出来る所を探して、深めていけば良い」と言ってくれました。後から聞いたのですが、父はある親しいお客さんに「息子が仕事、跡やってくれるらしいわ」と、喜んで話していたと聞きました。
大学を卒業した年の、4月1日。正式に父の元に入門しました。最初は、明らかに子どもが作ったような、寸法だけがどうにかあったようなものしか作れませんでしたから、そうしたものは容赦なく、「火の中に放り込んでこい」と言われました。また、私が少しでも気を抜こうものなら、ここにある「矯め木」で頭をゴツンとやられました。厳しい父でした。
今私が座っている場所は、火入れのとき父と対面に座っていた当時の私の定位置で、今もそのままになっています。父が座っていたところの方が、作業するには具合が良いのだと思うのですが、なんだかやりにくくて……。土壁だった壁も板に変わりましたが、ここには、叱られながら仕事を覚えていった思い出が染み込んでいます。自分の指先の感覚や、手の動きを感じて、まず体で覚えていく。そして勘所を掴んでいく。叱られる。その繰り返しでしたね。
――師匠に叱られ、体で覚えながら……
川崎幹生氏:
道具づくりからはじめて数年後の昭和60年、28歳で父の脇名である「玉成」を継いで、竿師として出発しました。……「玉と成る」これからの自分にふさわしい名前に思えました。それから父の銘である「東峰」を継ぐまで……その間に様々な出来事がありましたが、涌き起こってくる色々な想いと葛藤しながら、35年が経ち今に至ります。