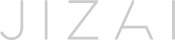道具屋のこだわりは「お客の声」を聴くこと
――覚悟は、磨かれていくものだと。
野本公敬氏:
そうですね。だから「お客さんの要望を聴く」ことが唯一のこだわりかもしれません。職人さんの中には、「お客さんを選ぶ」っていう人もいるけど、うちはあくまで道具屋。私は芸術家でも作家でもありません。お客さんの要望を聞いてナンボです。
また、お客さんだけでなくすべての人に対して「(釣りを)知らない人は、知りません」なんていうスタンスじゃ、釣りを楽しむ土壌も、広がらないと思っています。この世界を愛しているのなら、オープンにしていかないと。そういう姿勢でいると、いずれ社会から孤立してなくなっちゃいますしね。
竿の話だけじゃなくて、うちが400年近く代々続いてこられているのも、その時代その時代で、色んな人たちの声を聞いて、それに応えることで「生かされている」からじゃないかなって、そう思いますよ。
実は一時期うちにも「どん底」と呼べるような時期がありました。カーボン製の竿が流行した頃で、問屋さんが竹の竿をまったく扱ってくれなくなったんです。作っても売る場所がなければ、無いのと同じ。家業の危機です。そんな時に、タイミングよく「うちで販売してみませんか」と声をかけてくださったのが、日本橋高島屋さんだったんです。おかげで、販売を再開できただけでなく、対面を通じてオーダーを承けるというスタイルも確立することができました。この時も、「応える」ことによって助けられたんだと思います。
――お客さんの声を聴き、それに応える。
野本公敬氏:
お客さんは時に奇想天外な発想で、夢を持ってやってきてくれます。この世界に入ってもう50年以上になりますが、一本の竿を通して、お客さんとはたくさんの思い出があります。数百万円のお金を積まれて「これで頼む」と言われたこともありますし(そんなにかからないと普通の値段を提示したら驚いていました笑)、印象的だったのは、なんて言えばいいのかな、ルンペン。今で言う路上生活者の方が来られた時のこと。
盗まれないようにボタンにしまい込んだ一万円札を五枚取り出して、「これで作ってくれ」とお願いされたんですよ。「お客さんを身なりで判断しちゃいけない」って、いつも親父から言われてはいましたが、さすがに驚かなかったといえば嘘になります。もちろん、精一杯作らせてもらいました。出来上がったカワハギ竿を渡した時、「これで本望だ」と言われたのが、忘れられませんね。
だから、私が頑固になる場面は、自分のことというより、お客さんからの要望に対してです。要望に寸分違わぬものを作ろうと必死になります。竿づくりは、お客さんに出会ったときから始まっています。そこに受け継いだ技術や技を、全力で注ぎ込む。それが私のこだわりです。
一本の竿を通して多くの人に出会い、生きていく
――1本の竿を通して、色々な出会いがありました。
野本公敬氏:
竿づくりはお金儲けにはならないかもしれないけど、色んな人に出会えて、楽しかったと思いますよ。特に東日本大震災の時は、そうした出会いの絆を強く感じました。家族も家も流されて、途方に暮れていた仙台のお客さんが、数年後「竿、作ってくれないかな」と言ってきてくれた時は、この仕事をやって来てよかったと、つくづく感じたものです。
私は常々、釣りは世の中が平和じゃないとできない、平和産業だと考えています。言ってしまえば、無くたって死にはしないもの。でも、なくては困るものでもあるんです。竿を眺めるのも釣りのうち。震災の影響でまだ、海や川へは近づけない時も、心の支え、気が紛れるとおっしゃっていました。
そういえば、ある時、お客さんから「老けたね〜」と言われたことがありました。43歳から百貨店に立っていた私も、20年以上が経ちいつの間にか、頭の毛が真っ白になっていたんですね。でも、それはお客さんも同じ。むしろ大抵私より年上なのですが、竿を作りにいらっしゃる時の気持ちは、若い頃のままなんです。ですから、それ以来、毛染めをして、なるべく当時の空気を壊さないようにしていますよ。
いつも思うのですが、お客さんが童心に帰ったかのような、手にした時の「満面の笑み」というのは、やはり職人冥利に尽きるものです。だから、昔からの百貨店などでの対面、オーダーメイドというのは、求めてくれる人がいる限り、続けたいですね。ただ「コツコツ」という言葉は、なんとなくしみったれた感じがして嫌いで、また「〜すべき」なんていうのも続かないので、楽しみながら続けたいですよね。
――そうして、旭信の竿づくりも新たな世代に受け継がれていきます。
野本公敬氏:
ありがたいことに、今は次期五代目である息子が、すでに一緒に働いています。「釣り」を取り巻く環境も変化していますし、釣りだけでなくたくさんの道楽が、世の中にたくさんある中で、私たちの釣り竿が、どのような位置にいられるか。その時代その時代にあったやり方があると考えています。ですので、代々受け継いできた技術と技、そして「謙虚に聴いて応えること」を伝える以外は、やり方は次代に任せようと思っています。文化も道具も、そうやって進化してきたはずですから。
(インタビュー・文 沖中幸太郎)